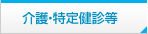Q&A
Q1. ORCAとはなんの略ですか?
Online Receipt Computer Advantage(進化型オンラインレセプトコンピュータシステム)の頭文字を採っています。
ただし、製品の名前ではなく、今後の医療のIT(Information Technology)化というものを、レセプトコンピュータ(以下レセコン)の高機能化という切り口からスタートして考えた日医のプロジェクトの名称です。
主要な製品として、「日医標準レセプトソフト」(以下「日レセ」)というレセプトソフトを開発、無償提供中です。
ただし、製品の名前ではなく、今後の医療のIT(Information Technology)化というものを、レセプトコンピュータ(以下レセコン)の高機能化という切り口からスタートして考えた日医のプロジェクトの名称です。
主要な製品として、「日医標準レセプトソフト」(以下「日レセ」)というレセプトソフトを開発、無償提供中です。
Q2. 入院には対応していますか?
入院に対応した日レセは、2003年度より提供しております。
最大では400床クラスの病院でお使いいただいております。
最大では400床クラスの病院でお使いいただいております。
Q3. Windows や Macintosh の環境では動かないのですか?
サーバには、Linux(リナックス)で動くパソコンが必要です。
クライアント(端末)に関しては、WindowsやMacintoshでの利用が可能です。
医療機関内の標準機器構成はパソコン2台を推奨しています。この2台は、サーバ(メイン・サブ)兼クライアント(端末)として利用し、Linux上でのみ動作します。3台目以降は、純粋なクライアント(端末)となります。
サーバ用プログラム、クライアント用プログラムのいずれも、他の言語やOS(オペレーティングシステム)への移植が可能ですが、クライアント用のプログラムには、特に移植性の高い設計(コーディング)をしています。
「オンラインレセコン」の名に示すとおり、本体プログラムはサーバにありますので、遠隔地にサーバを置き、手元にクライアント(端末)を置くような運用も可能となります。
クライアント(端末)に関しては、WindowsやMacintoshでの利用が可能です。
医療機関内の標準機器構成はパソコン2台を推奨しています。この2台は、サーバ(メイン・サブ)兼クライアント(端末)として利用し、Linux上でのみ動作します。3台目以降は、純粋なクライアント(端末)となります。
サーバ用プログラム、クライアント用プログラムのいずれも、他の言語やOS(オペレーティングシステム)への移植が可能ですが、クライアント用のプログラムには、特に移植性の高い設計(コーディング)をしています。
「オンラインレセコン」の名に示すとおり、本体プログラムはサーバにありますので、遠隔地にサーバを置き、手元にクライアント(端末)を置くような運用も可能となります。
Q4. なぜ、Linux(リナックス)を採用したのですか?
Linux はオープンソースのOS(オペレーティングシステム)であり基本的に無料です。
ネットワークを前提としたOSです。
市販の安いパソコンが利用できます。
ブラックボックスの部分がありません。
日レセを含め全てがオープンソースであるが故、セキュリティーホールの発見・修正が早く、クラッキングのリスクを最小にできます。
ネットワークを前提としたOSです。
市販の安いパソコンが利用できます。
ブラックボックスの部分がありません。
日レセを含め全てがオープンソースであるが故、セキュリティーホールの発見・修正が早く、クラッキングのリスクを最小にできます。
Q5. Linux やパソコンに対する深い知識が必要ですか?
設置やメンテナンスには、日医総研 日医IT認定サポート事業所(以下、認定事業所)をご利用頂くことを推奨します。
医師ご自身がパソコンに詳しい場合は、独力で設置・運用していただくことも可能です。
Q6. 都道府県による医療費助成制度やレセプト出力の違いについて
都道府県別の地域公費などへの対策として、対応したプログラムを47都道府県毎に開発、公開を進めています。
地元の企業を地域の医師会で育てて頂いている側として、認定事業所が独自に開発、提供している地域もあります。
地元の企業を地域の医師会で育てて頂いている側として、認定事業所が独自に開発、提供している地域もあります。
Q7. ORCAネットワークへの接続はどうなりますか?
接続のための専用の機器(ルータなど)は必要ですか? インターネットへの常時接続もしくはマスタ更新などが必要な時のみの接続を推奨しています。
接続方式については、随時に高速・低価格の商品が出てくるため特定しにくい状況です。
基本的には、ブロードバンドで帯域を確保できるものであれば問題ありません。すでに、光ファイバ、ケーブルテレビ、ADSLなどで常時接続を行われている医療機関であれば十分対応できます。
接続のために必要な機器(ルータなど)については、新たに購入の必要がない方式を採用しています。
接続方式については、随時に高速・低価格の商品が出てくるため特定しにくい状況です。
基本的には、ブロードバンドで帯域を確保できるものであれば問題ありません。すでに、光ファイバ、ケーブルテレビ、ADSLなどで常時接続を行われている医療機関であれば十分対応できます。
接続のために必要な機器(ルータなど)については、新たに購入の必要がない方式を採用しています。
Q8. インターネットを利用した場合の通信経路のセキュリティについて
しかし、ハッキング技術も進化し、OSレベルのセキュリティ問題が発生する可能性は常にあります。
そこで、センター運営による最新のセキュリティ対策をとっており、同時にセキュリティ運用ポリシーなどを策定しています。
これをORCA導入医療機関、協力業者にアナウンスすることで、運用面からもセキュリティの確保を図っています。
Q9. 日医でのデータ利用について
調査や統計が必要となった時には、データをバックアップとは別に収集することになります。
これらは当然ながら医療機関の承諾なく収集することはありません。また、患者への了解の取り方などを規定した上で、個人を特定できる情報を除いた形でのデータ収集として「定点調査研究事業」をおこなっております。
Q10. 各医療機関で必要な主な機器構成は?
サーバ兼クライアント(端末)
3台目以降のパソコンを接続する場合は、純粋なクライアント(端末)となります。
- パソコン2台推奨(本体+バックアップ機としても利用)
- プリンタ1台
(Windowsプリンタと言われる、Windows専用のプリンタ以外であれば、GhostScriptと言われる方法を用いることで、一般市販のプリンタで問題ありません。PostScript対応プリンタを導入することが可能であればそちらを推奨します。)
3台目以降のパソコンを接続する場合は、純粋なクライアント(端末)となります。
Q11. サーバおよびクライアントとなるパソコンに必要なスペックは?
推奨最低環境スペックは以下のとおりです。
【サーバ】
【クライアント】
【サーバ】
- Ubuntu18.04/20.04/22.04
- 64ビットCPU :2GHz以上、クアット以上のコアプロセッサ
- メインメモリ:8GB以上
- ストレージ :500GB以上
- 解像度 :1280X800 以上
【クライアント】
- ■サーバがUbuntu18.04/Ubuntu20.04の場合
- 64ビットCPU :2GHz以上、デュアル以上のコアプロセッサ)
- メインメモリ :4GB以上
- ストレージ :200GB以上
- クライアントOS(64bit) :Windows10/11、macOS 11/12/13/14、Ubuntu18.04/20.04
- クライアントプログラム :OpenJDK/glclient
- ディスプレイ解像度 :1280X800 以上
- 64ビットCPU :2GHz以上、デュアル以上のコアプロセッサ)
- メインメモリ :4GB以上
- ストレージ :200GB以上
- クライアントOS(64bit) :Windows10/11、macOS 11/12/13/14、Ubuntu22.04
- クライアントプログラム :Google Chrome
- ディスプレイ解像度 :1280X800 以上
- 64ビットCPU :2GHz以上、デュアル以上のコアプロセッサ)
- メインメモリ :4GB以上
- ストレージ :200GB以上
- クライアントOS(64bit) :Windows10/11、macOS 11/12/13/14
- クライアントプログラム :Google Chrome
- ディスプレイ解像度 :1280X800 以上
※ クライアント端末に同居するシステム(電子カルテ等)がある場合は、同居システムの推奨スペックも加味したうえで環境構築してください
Q12. Linux のディストリビューション(パッケージの種類)について
Q13. 機能拡張のしくみ
OS(オペレーティングシステム)とアプリケーション(日レセ)のクッション材となるプログラム(ミドルウエア)を、レセプトソフトとは別にオープンソースとして提供しています(共通規格部分)。
これは、どのようなOS、どのような開発言語でつくられたプログラムでも運用を可能とすることを目指したシステムです。
共通規格部分はいくつかのモジュールに分かれています。
これは、どのようなOS、どのような開発言語でつくられたプログラムでも運用を可能とすることを目指したシステムです。
共通規格部分はいくつかのモジュールに分かれています。
- クライアント(端末)の入出力機能(画面入出力定義はXML)
- クライアントとサーバの通信機能
- アプリケーションの入出力機能
- ワークフローコントロール機能
Q14. 既設のシステムや他の電子カルテとの連携は?
レセコンと電子カルテの交換規格(CLAIMなど)や、医療情報交換の XML 規格など医療の世界での共通規格が定まりつつあります。
日レセでもこれらの規格を取り入れ、他システムとの連携が可能になるよう進めて行きます。
既存の検査機器等で上記の規格に対応していない場合でも、各メーカの規格や連携記述の公開があれば順次対応していきたいと考えています。
日レセでもこれらの規格を取り入れ、他システムとの連携が可能になるよう進めて行きます。
既存の検査機器等で上記の規格に対応していない場合でも、各メーカの規格や連携記述の公開があれば順次対応していきたいと考えています。
Q15. 既存のレセコンからのデータ移行について
大手メーカ製のレセコンに関しては、大抵、データ移行の手法が確立しています(有償です)。
該当外の機種であれば、データ移行の手順解説書を公開しますので、それを元にして認定事業所、または既存機のベンダーに抽出・移行をして頂くことになります。 なお、レセコンからのデータ移行については、メーカ、形式、年代により難易度が大きく異なります。
既存のレセコンに登録されている患者の頭書き情報などは、医療機関にとっては重要な資産であり、データの抽出を要求する当然の権利があります。
該当外の機種であれば、データ移行の手順解説書を公開しますので、それを元にして認定事業所、または既存機のベンダーに抽出・移行をして頂くことになります。 なお、レセコンからのデータ移行については、メーカ、形式、年代により難易度が大きく異なります。
既存のレセコンに登録されている患者の頭書き情報などは、医療機関にとっては重要な資産であり、データの抽出を要求する当然の権利があります。
Q16. 開発言語について
共通規格部分は C言語で書かれています。
レセプト部分は従来よりレセコンの開発によく使われてきたCOBOLで書かれています。これには人的資産、既存のプログラム資産の再活用も可能となるよう考慮した結果です。
これらはオープンソースとして仕様とソースを公開しますので、他の言語にも移植が可能です。
レセプト部分は従来よりレセコンの開発によく使われてきたCOBOLで書かれています。これには人的資産、既存のプログラム資産の再活用も可能となるよう考慮した結果です。
これらはオープンソースとして仕様とソースを公開しますので、他の言語にも移植が可能です。
Q17. 点数改正時の費用、対応時間はどうなるのか?
従来、点数改正は旧厚生省からの発表後、短期間での対応を求められるため、システム開発者の改正時の負担も大きく、高額かつ時間との争いでした。
ORCAプロジェクトでは、改正時のマスタやプログラムを無料で提供する上、ネットワークを使った円滑な運用が可能です。
ORCAプロジェクトでは、改正時のマスタやプログラムを無料で提供する上、ネットワークを使った円滑な運用が可能です。
Q18. 普及が遅いのではないか?
レセコンは通常約5〜8年間隔でリプレイスされるため、爆発的に普及するものではありません。
Q19. 導入した会員にのみメリットがあるのでないか?
ORCAプロジェクトの効果により、メーカ製レセコンの市場価格は大幅に下落していると思われます。
今後は定点調査などの協力をお願いし、医療政策の提言や検証に役立つデータを収集します。
今後は定点調査などの協力をお願いし、医療政策の提言や検証に役立つデータを収集します。
Q20. 既存のレセコンメーカを潰すのか?
オープンソースであるため、既存のメーカも自由に扱えます。
Q21. インターネット接続しなければ動かないのか?
日常業務で常時接続する必要はありません。マスタ更新やプログラムの更新が必要な時にインターネットがあると便利です。
Q22. 日医に自院の診療データが筒抜けになるのでは?
勝手にデータが日医に流れるようなことはありません。
日医のデータ収集である定点調査研究事業については、改めて志望者を募り、データ送信の意志を確認しております。
日医のデータ収集である定点調査研究事業については、改めて志望者を募り、データ送信の意志を確認しております。
Q23. 電子カルテは開発しないのか?
電子カルテは既に20社を超える製品から選択できます。
全診療科診療スタイルに合わせる必要がある日医版電子カルテの開発はコスト的に困難です。
市販製品の日レセとの接続を支援しています。
全診療科診療スタイルに合わせる必要がある日医版電子カルテの開発はコスト的に困難です。
市販製品の日レセとの接続を支援しています。